今回の質問の振り返り
4回目ということで気分的に余裕を感じていたが、質問内容及び当日のやり取りの原稿づくりの締め切り直前となった。あれこれと市民の方々からいただく意見やこれまでのやり取りも含めて内容を最後まで絞り切れなかった。
財政健全化については、市民を我慢だけに追いやるようなやり方ではなく他の方法があったのではないとの思いが強く。あそこまで内外に「財政難」ということをアピールする必要性を感じない。大胆な一律カットで財源(財政調整金)は確保できるかもしれないが、定住・経済効果等の面での負のイメージによる損失がかなり大きいのではないかと危惧するところです。引き続き、検証する必要があります。
新年度予算では、無償化・臭気対策等の公約の予算づけはされているようですが、多くの市民が新市政に期待に値するものでしょうか。失礼な言い方ですが、夢が無いから現実の目の前の課題を解決しているような気がしてなりません。お金が無いので無い袖は振れないという決め文句もしかり。
「対話」について
これまでの議会と市長との意見の食い違い、議会が擁立した市長と言うこともあり、今回の財政健全化についても十分な議会内での議論がされているのか?私が言うことではないが、1人会派としての意見は申し述べるが、議会の要望としてそれが反映されているかは疑問と言わざるえない。数の原理が事を制する感がある。「対話」「対話」と言いながら、大胆な健全化案を提示し、最初の説明では「あくまで案ですから」と回答し、意見はパブリックコメントで!パブリックコメントが500件ぐらい寄せられると、それの回答をするだけで「対話」が成立したと言えるのか?
そもそも、異なった意見があるのはあたりまえの話でお互いのことをそれほど知らなかった行政と団体がこのプランによって説明のために接点が出るわけですが、削減ありきで話が進むので話は当然平行線となります。信頼関係などはそもそも構築されません。市民のやる気をこんなやり取りでそぐ形になるのは不幸な話です。
今回、市民の方々から多くの意見をいただきました。関係団体に関わることは名指しでは質問が逆効果になることもあるので突っ込んだ話にならない部分もあり、かなりぼやけた形になった。迫力に欠けるという感想もいただいた。4回目ということで少し油断をしていたかもしれない。まだまだだなと自己反省するばかりです。
3月11日(火)に3月議会定例会の質問にたちました。当日用意していた質問原稿から当日のやりとりを説明させていただきます。
最後の質問者になります。今日は14回目の3月11日です。毎年、明日への架け橋Kasaokaが笠岡駅前で14時から東日本大震災追悼式を開催します。追悼式のご案内をして、議長のお許しをいただきましたので、質問に入りたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1項目目は財政健全化についてです。
(1) このたびの笠岡市財政健全化プランに対してのパブリックコメントはかなりの数に及んでおり,総論的なものや各論のもの多々あるが,そもそもの財政健全化の原因・規模やその方向性(削減の明確な基準)についての丁寧な説明がされていないのに,財政再建団体となった北海道夕張市のようになるという脅しのような手法で,押しつけの健全化プランを提案している。そもそもそのスタートに大きな疑問を持っている。
また,パブリックコメントへの回答のみで済ませるのは,市長の「対話」という方針からは、かけ離れていると思うが,市の見解を尋ねる。
(2) 総論の部分でもいろいろな意見が出されていた。しかし,総花的に,このままでは単年度赤字となり,財政調整基金を取り崩して補填していると,令和⒑年には財政再建団体になる,との一律な回答でした。
根本的な財政状況について明確な回答がないままに,年間10億円,10年間で100億円の赤字が生じるので,財政再建団体にならないためにこの財政健全化が必要という説明に納得できない方が多数いらっしゃる。そうであるならば,本市の財政の現状を,財政担当者から市民にお知らせする財政説明会等の開催も必要だと考えるが,市の見解を尋ねる。
(3) 人口減少社会に加えて,昨今の物価の急上昇に伴い,財政のやりくりについては苦慮する所ではある。しかし,対市民との交渉をする職員も削減ありきで,「財政が苦しいから」という理由によって,市民との「対話」ではなく「対立」になっている。現状を一番よく知っている担当部の裁量がなく,一律削減の指示の下,団体とのやり取りが平行線で無駄を重ねている現状についてどう考えるか。
(4) 特別交付税措置で,国からの財源確保されている事業については継続の方向性で取り組まれているようだが,今まで一般財源で行っていた事業でも,特別交付税措置を講ずることにより継続できる事業については復活を検討する余地はないか尋ねる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
市長はあのパブリックコメントをどう受け止めていらっしゃいますか?私は、住所も名前わかる真摯に財政のことを考えて下さる市民の方々こそ市長の言われる、この財政の大変な特に一緒に考え行動する市民お一人お一人ではないかと思うのですが。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
今議会の市長答弁の中で気になった回答に市役所はサービスセンターではない。色々なサービスがあるから笠岡市に来るというサービス合戦で人を取り合うようなことは考えていない。
これまで地域で活動されている方々の活動が財政健全化で制限される現状の中で、財政難だから予算は削減するけど、市民はサービスを受けるだけの存在ではなく、行政と一緒に作り上げることが必要。
行政の仕事はあくまでも必要なインフラ整備という意味のことをおっしゃていました。果たして周囲も含めてほとんどの自治体がいろいろな取り組みで人口増を考え実践している中で果して笠岡市が生き残っていけるとお考えですか?お尋ねします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
市長は財政健全化の説明会の中でこのままいくと「夕張のようになる」と市民への危機感を煽ると言っても過言でない説明をされています。果たして夕張になるのですか?
・・・・・
夕張以外に財政再建団体になった市町村がありますか?お尋ねします。
副市長答弁、夕張は払拭決算であのようなことになっていますが、それ以前は何件かあったと聞いています。
・・・・・
夕張以後は内にも関わらず「夕張のようになる」という表現をされるのか?お尋ねします。
市長答弁:私から夕張のようになると言ったことはないと思います。市民の方が説明会の中でそのような表現があったので、そのようになる可能性があると・・。
・・・・・
そして、財政健全化の目的が財政再建団体となるから仕方ないでは到底理解出来ません。
・・・・・
市民を必要以上に煽ることになったと思います。また、同時に日本全国に笠岡市が財政難ということを自ら知らしめるマイナス効果が大きかったのではないかと危惧しています。
パブリックコメントの中にも笠岡市の歳出予算が市の経済を回している側面やコミュニティを支えている側面があることへの影響についてはどうお考えですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「対話」とは何かについてです。パブリックコメントを単なる健全化のための過程と捉えてはだめだと思います。
市民は直接公の場で議論できない間接民主主義なので、議員がその代弁者として、それを聞いている市民ひとり一人が納得できるやり取りをすることで市長のおっしゃる「対話」に繋がるのかなと思います。
また、直接市長がすべての団体への説明をするわけにはいかないということでその「対話」を代行するのは「職員」です。市長の分身として財政の見通しや削減理由を職員が十分腹落ちして「対話」に臨むことが必要です。
今のやり方は「通知」から結論ありきの「説得」になっています。財源を確保するための財政健全化は「手段」であって、財政調整基金を増やす事が「目的」であってはなりません。
健全化の「目的」は最優先される施策は何であるか?最優先する施策を残すために、財源が限られているので優先順位が低いものから削減するということでなければ、市民は納得できません。
(2)の項目にも関連しますが、私が申し上げたいのは、本当に真摯に考えている人が疑問に思っていることに対して納得のいく回答をする気持ちがあるか無いか?市長との座談会で折に触れて市長から説明すれば済む話だとは思えないのですが。いかがお考えですか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
提案ですが、私どもが財政勉強会を企画する中で、笠岡市の財政担当の方に来ていただいて一緒に財政について考えるといった場面を作ることは可能でしょうか。
各種団体から申し込みをいただいた市長との出前講座等の際に私から丁寧に説明しているので、あらためて担当が説明する場をつくるつもりはない。
必要であれば、市長との出前講座を申し込んでいただくなかで丁寧に説明する。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3)福祉事業で削減を検討している事業については一律カットではなく最初からこの1年をかけて内容の精査を先にするべきだったのではないか。財政部局からの一律のカットありきで担当課が団体へ説明に回っても「対話」ではなく「説得」なっているのではないかと思います。これまで委託事業や補助の内容を精査することなく、事業に対する認識が浅いうえに、人間関係も構築されていない関係性では納得できず平行線になっているのではと推察します。いかがお考えですか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4)項目について
今予算も特別交付税措置で国からの交付税で賄える事業をいろいろと計画されています。財政健全化が無ければそこまで考えることもなかったのが現状ではないかと思います。企画政策課が笠岡市の政策作りのづくりの部分でイニシアチブをとっていただき、積極的に補助事業や交付税措置による財源確保の取組機運を全庁的に進めて欲しいと思います。これについて何かお考えがあればお示しください。
・・・・・
副市長を中心に大胆な財政健全化プランが構築されましたが、副市長は岡山県の職員出身であり、県庁とのパイプが太いと思われますが、今回の財政健全化について県へのアプローチをされていればお聞かせください。
・・・・・
笠岡市にとっても県との連携は大きいと思います。パブリックコメントの市民の方からの意見にもあったのですが、井笠の振興局の地域振興室がなくなってから県とのやり取りが激減。岡山県の財政再建のあおりではないかと思っています。島の活性化の取組の気かけは県のフロンティア事業予算でした。いろいろと調べていると、高知県では2003年度7名から始まり、県の職員を県内の7ブロックに64名の地域支援企画員を配置して、市町村の集落活動センターを支援する取り組みをされています。
この市町村の集落活動センターが地域の核(小さな拠点)と位置づけて県の補助メニューも活用して農業・福祉の専門分野を超えての職員配置がされています。地域コミュニティに県の職員がサポートに入り、地域の核といえる集落活動センター構築で住民自治の取り組みに寄り添い方の支援を行っています。
副市長の県への大胆なアプローチでこのピンチに県との新たな関係構築を進めていただきますようお願いします。今考えられる県との連携等あればお聞かせください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
福祉と子育てについては削減していないと先の12月議会の私の質問に対しての市長答弁でおしゃいましたが。これだけ多くの福祉関係事業へのパブリックコメントが寄せられている現状をどうお考えですか。
全ての福祉・子育ての予算を削減していないとは言っていない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
この項の最後にお尋ねします。福祉を守る心は市長の中にあるのかお伺いします。
あります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2項目め
新年度予算について
(1) 笠岡市財政健全化プランにより,10億円程度の削減と5億円の行革債の借入れをするという中で,新年度一般会計予算は,過去最大の275億円になると報道されている。市民の方々に対しては,これまでの財政健全化に矛盾する内容となっている。その内容を尋ねる。
(2) 財政健全化の中での栗尾市政の初めての新年度予算となる,市長が目指す笠岡像,そして,何よりも優先した新年度の施策について尋ねる。
(3) 国の物価高騰対策に準じて,本市でも対応策を各分野にわたり検討され,具体的に施策として提案されている。
(ア) 笠岡諸島の離島航路燃料価格高騰対策支援事業として,補助航路以外の航路事業者への支援が予定されている。
航路再編への事業者との話し合いを,市長自らも出向いて進めるとのことであったが,その進捗状況を尋ねる。
(イ) 笠岡市内の指定管理事業者において,物価高騰や人件費アップに伴う指定管理料金の赤字補填等について,考えを尋ねる。
(ウ) 蛍光灯の2027年問題として,製造・輸出入が2027年までに段階的に禁止される。それに伴い,省電力化の観点からも,LEDの設置が事業所・家庭・街路灯に至るまで幅広い対応が求められる。これらに関連した物価高騰対策の事業について尋ねる。
(4) 観光施策について,令和7新年度の観光事業の目玉についてお尋ねる。
(5) 地域コミュニティ等について
(ア) 令和7年度に,まちづくり協議会や公共施設の使用料見直しを計画する方向性を持っているとの話があったと思うが,今後の予定について尋ねる。
(イ) 今井地区を想定して進められているまちづくり協議会と公民館との拠点づくりの方向性について尋ねる。
(ウ) 敬老会・市美展の今後について尋ねる。
(2)ピンチはチャンスとも言われます。パブリックコメントの中にもありましたが、笠岡市政で初めて来年度の予算の事について前年度にこれだけ多くの方々が注目して、意見を言う場を設けた点においては、これまでの歴代市長がなしえなかった事を実施されている点で多いに評価されてしかるべきという意見もありました。
しかし、削減のみの内容協議では市民は納得できません。一般市民は「我慢の先にある夢」を想像するだけでも元気が湧いて来て、協力体制の構築に資するものである。というコメントにもあるように、笠岡市の新しいリーダーとして「将来はこの様な姿の町に仕上げたい」という具体的な姿・夢を語っていただくことは出来ますか?お尋ねします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(3)国の物価高騰対策について
(ア)この事業全般の事業説明と実施時期、補助申請の方法等について尋ねる。
具体的な検討プランが無いと交渉のテーブルは設定しにくいと思われますが、物価高騰対策に関連しての説明会を船舶業者を一堂に会する機会として位置付けて開催してはどうか。(具体的な実施時期等について尋ねる)
(イ)指定管理について
指定管理を5年契約で受けている事業者にとってもこの物価高騰の煽りは受けていると思います。その赤字補填についての一定のガイドラインはあるのか?
ガイドラインはないが、その都度事業者と協議している。
人件費の問題や有資格者が必要な施設については人材確保の面からも一定の水準を確保することも必要となってきます。利用促進が図られればその分経費も上がります。住民ニーズのある施設については経費だけでなくその内容も十分見極めてもらっての配慮をいただければと思っています。当初からこれだけも上げているだけでなくよりその施設の目的達成のための想いを共有を心がけて欲しいと考えます。
各事業者と個別に協議を進めます。
(ウ)蛍光灯2027年問題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(4)観光施策について
笠岡市の観光の特徴は「笠岡諸島」だと思っています。自然環境と伝統行事の他に一番の資源は「島の方々」。今年度も六島や北木島で人材育成事業を展開させていただきました。私の島に対する想いは「島は陸地部の20年先取り」過疎・高齢化・地域課題の先進地。「島は日本の縮図」だと思っています。
先日の六島の水仙が咲いていないという話も出ていましたが、現在より一層の担い手の減少で景観保持の活動も地域だけでは成り立っていかない状況です。
話のすり替えをして如何に地域の方々にその気になって実践してもらうかが重要です。島民の数が減って月100人が船を利用していた人が50人になったらどうするか?その減少分50人を外から呼んで来ないと島の交通手段としての船の運航が確保できないとします。島の島民一人一人が観光的な動きをして観光客を50人確保することが自分の交通手段を確保することになると言っています。
恒例のツアーも受入れが出来ないという現状もそう遠くありません。観光振興という視点だけでなく、体験メニューとして観光資源を共に創る・整備するという視点での取り組みが必要となって来ています。「観光」から「体験」→「関係人口」づくりを意識しての取り組みが求められています。
栗尾市長は島の地域コミュニティ・観光振興についてどうお考えですか?
島に限ってのことではなく観光は笠岡市全体の事で考えている。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
私はずっと島の可能性しか感じない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5)地域コミュニティについて
(ア)
パブリックコメントにもまちづくり協議会の是非についてのコメントが見受けられます。地域によってはあまり機能していないところも見受けられるのが現状であるが、今後住民自治の観点から必要な施策ではあるが、令和7年度のまちづくり協議会への財政健全化による減額等はないのか?今後のまちづくり協議会の方向性について尋ねる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・平成20年の笠岡市自治基本条例の策定、平成22年の「笠岡市地縁組織との協働システム構築計画」に基づき、平成24年4月から市内24地区でまちづくり協議会が本格スタートしています。令和5年12月にまちづくりについての政策提言がなされていますが、その提言を受けて以後のまちづくり協議会の取組にどう生かされているかお伺いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・市長の持つ小規模多機能自治のイメージをお尋ねします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(イ)今井の取組については小規模多機能自治のモデルと言えるのではないか?
議会のまちづくりの政策提言の中には活動の重複がないように組織を再編成、地域の核となる場所を一つにして意見交換・情報交換が出来る場所の確保。集落支援員制度を活用した事務局機能の確立。活動報告や会計の公開。小規模多機能自治の啓発・啓蒙と書かれています。
こういった提言に基づいて、集落支援員制度の活用や「小さな拠点」としての核となる施設の整備を岡山県のいきいき拠点整備事業を活用して令和6年・7年で実施している。いわゆる小規模多機能の施設整備という面ではモデルであると思っているが、なぜそういった先進的なまちづくり協議会の実践を再編に活用しないのか。
地縁組織と志縁組織について再質問をしました。
地縁組織はいわゆる「まちづくり協議会」との地域住民で組織するもので、志縁組織は
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(ウ)敬老会について・・
聞こえてくる話や削減の説明の中に対応する人の声として負担を感じているという表現があったが、これを中止の理由に上げるのは気遣いが必要ではないか。本来の敬老の目的を見失っている。
だんだん高齢者が増える中で方法や手段は変える必要があったのではないか。これもこの時期の中止は財政難だから敬老会を中止したと言われても仕方ない。お金がないからできないというのは簡単なことで、本当に必要な仕事として考えていたならば形を変えてでも継続する方法を提案するなどの方法もあるのではないでしょうか。止める時は代わりの事業を提案して今までのマンパワーに次なる役割を引き継いでもらうなどの工夫はするべきではないでしょうか?お尋ねします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
市美展・・来年度から中止と搬入の時に聞いた。初回から出品しているので立ち上げの時の想いもあり残念でしかたない。委嘱であり、出品料を1200円払って毎年出品していた。予算を削減して継続とおもっていたが・・・。
1200円出品料を払って出品しており、予算的にも出品者が協力していた。公募展な性格があり、文化レベルを上げたいという意識もあり、文化祭とは違うという認識でした。文化連盟等との協議の中での中止だとは思うが思い入れのある人はその決定に納得がいかない。この時期での中止は、理由をどう整えても「財政難での中止」と言われてもしかたない。そのあたりをどうお考えですか。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
最後になりますが、栗尾市長の初めての新年度予算です。今回は財政健全化で財源確保が最優先だったかもしれません。
「真のクレーマーは明日の協力者」私みたいに苦言を呈するものはそれなりに自分自身にもプレッシャーをかけて何かやろうと考えています。最初から結果を求めては何もできません。何か課題に立ち向かい行動を起こすことで一人でも応援してくれればそれでいいと思います。職員のチャレンジを一つでも多く後押ししていただき市役所が動いているな。金が無い時は頭を使え!頭が無い時は汗をかけ!現場で市民と一緒に汗をかくことで見えてくることは必ずあると思います。共に頑張りましょう!


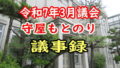
コメント