それでは,最後の質問者になります。
先ほども黙祷がありましたが,今日は14回目の3月11日です。犠牲になられた多くの皆様方に追悼の意を表したいと思います。今年も明日への架け橋Kasaokaが笠岡駅前で14時30分から東日本大震災追悼式を開催します。御案内をさせていただき,議長のお許しをいただきましたので早速質問に入りたいと思います。よろしくお願いします。
まず,第1項目めは財政健全化についてです。
このたびの,笠岡市財政健全化プランに対してのパブリックコメントはかなりの数に及んでおり,総論的なものや各論的なもの多々あるが,そもそもの財政健全化の原因,規模やその方向性(削減の明確な基準)についての丁寧な説明がなされていないので,財政再建団体になった北海道夕張市のようになるという脅しのような手法で押しつけの健全化プランを提案して,そもそもそのスタートに大きな疑問を持っている。 また,パブリックコメントへの回答のみで済ませるのは,市長の対話という方針からかけ離れていると思うが,市の見解をお尋ねします。
○市長(栗尾典子君) 1項目めの1点目についてお答えします。
パブリックコメントでは多くの市民の皆様に関心を持っていただき,たくさんの御意見をいただきました。いただいた御意見につきましては,お寄せいただいた市民の皆様お一人お一人の思いを感じながら丁寧な回答をさせていただいたところでございます。
また,パブリックコメント以外においても,関係団体とも対話を重ね,プランの見直しの内容の修正も行ったところであり,今後も引き続き市民の皆様の声に耳を傾け,しっかりと対話し,夢と笑顔が広がるまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
2項目め,総論の部分でいろいろな意見が出されていた。しかし,総花的にこのままでは単年度赤字となり,財政調整基金を取り崩して補填していると令和9年には財政再建団体になるという一律な回答でした。 根本的な財政状況について明確な回答がないままに,年間10億円,10年で100億円の赤字が生じるので,財政再建団体にならないためにこの財政健全化が必要という説明に納得できない方が多数いらっしゃる。そうであるならば,本市の財政の状況を財政担当者から市民にお知らせをする財政説明会等の開催も必要だと考えるが,市の見解をお尋ねします。
本市の現在の財政状況につきましては,これまでも丁寧に説明を行ってまいりました。先日の代表質問でもお答えさせていただきましたが,令和7年度以降物価高騰等に伴う費用の増加に歳入が追いつかず,毎年収支不足が生じる見込みとなりました。特に,令和7年度においては約13億円の収支不足が生じる見込みとなり,その財源不足を補う財政調整基金が底をつき,赤字が発生する見込みとなりました。実質赤字比率は,令和9年度で早期健全化基準を超える17.7%,いわゆるイエローカードとなり,令和10年度には25.9%で,財政再生団体,いわゆるレッドカードとなり,国の関与の下,市が実施しているサービスに様々な負担や制限が生じる状況に陥ってしまいます。こういう状況を回避するために,このたび,財政健全化プランを策定し,健全化に向けた取組を進めようとしております。
財政の説明については,今後もホームページや広報紙,市長との座談会などを通じて,分かりやすい説明を尽くしてまいります。
3項目め,人口減社会に加えて,昨今の物価の急上昇に伴い,財政のやりくりについては苦労するとこではあるが,しかし対市民との交渉をする職員も,削減ありきで財政が苦しいからという理由によって市民との対話ではなく対立になっている。現状を一番よく知っている担当部の裁量がなく,一律削減の指示の下,団体とのやり取りが平行線で無駄を重ねている現状についてどう考えるかお尋ねします。
昨年11月に財政健全化プランの素案を公表し,その後約3か月の間,それぞれの部署においてもプランの最終案取りまとめに向け関係団体や市民の皆様と協議をし,対話を重ねてまいりました。短期間の調整であったことから,一部の事業についてはプランにおいて協議を継続するとした事業もございます。これらの事業につきましても,庁内での連携もより一層図りながら,今後も引き続き皆様と対話を重ねてまいりたいと考えています。
4項目め,特別交付税措置で国から財源確保されている事業については継続の方向性で取り組まれているようだが,今まで一般財源に行っていた事業でも特別交付税措置を講ずることにより継続できる事業については復活を検討する余地はないかお尋ねします。○議長(大月隆司君) ただいまの質問に対し,執行部の答弁を求めます。
このたびの事業見直しに当たっては,特別交付税措置を含め,国や県からの補助金など,様々な財源の確保についても検討を行いました。今後も引き続き社会情勢や財政状況を踏まえながら,事業の必要性を検討してまいります。
市長にお尋ねします。
市長は,説明の中で財政再建団体になるというふうな表現もされているようなんですけども,実際に夕張以外に財政再建団体になった自治体があるのかどうかお聞きいたします。
那須副市長。
財政健全化法ができて以降は夕張だけだという認識です。旧法の時代には,赤池町というところが財政再建団体になったという事例がございます。
守屋基範議員。
現在において,そういう団体がないということ,机上だけの算出で市民のそういうところをあおるというふうな感じの表現というのは好ましくないんではないかなと思うんですけど,いかがでしょうか。
栗尾市長。
皆様への分かりやすい説明ということで,財政見通しの中でも出てきているようなイエローカード,レートカードというような表現を使って今回も説明をさせていただきました。自治基本条例の中にもありますように,笠岡市が市民の皆様にきちんとした財政状況をお伝えするというのは責務というふうに感じておりますので,しっかりとした説明をしたことに間違いはないというふうに思っております。
○5番(守屋基範君) それでは,財政再建団体も含めて,10年で100億円という財政危機の報道も含めて,今の報道内容については笠岡市の今後の,例えば定住とか経済に与える影響とか,そういうことも含めてかなりな影響があるんではないかなと思っております。まず,市長,いろいろ対話ということを言われてますけれども,対話とは何かについてです。まず,パブリックコメントを単なる健全化のための糧と捉えては駄目だと思います。実際に,あれだけ多くの方々の意見がある中で,その中の一つ一つはかなり専門性もあるし,これから債権をするに当たっての大きな力になってくるんではないかなと思ってます。実際に,そういう一人一人お名前も分かるし,そういう方に対して実際に,私が言いたいのは総論の部分で,こうじゃないんかなみたいなことを住民の方が言われて,それが納得できない人もいらっしゃるんで,例えばなんですけども,市民団体とか,私どもが財政勉強会をしたときに財政担当者に来ていただいて,そういうことをお互いに話をする場,そういうことを設けることは可能かどうかお聞きいたします。
○市長(栗尾典子君) 再質問にお答えします。
現在も行っておりますが,市長との座談会を設けております。つい最近もある地域に出向きましてからの要望で,財政の健全化のことについての説明をさせていただいた上で,地域の方々との意見交換をしてまいりましたので,今後も引き続き市長との座談会をやってまいりますので,ぜひともお申込みいただきたいと思います。よろしくお願いします。
○5番(守屋基範君) 総論的な部分で,かなり市民の方々が詳しい内容も含めて書かれている内容は市長も読まれたと思うんですけども,ああいうところを市としてもそういうキャッチボール,私が行って話をしたときに,ついでにするわとかという感覚ではなくて,実際にそういう人たちを本当に大切にして,次の財政再建のために力にしていくという,何かそういう考えはないのか,お尋ねいたします。
○市長(栗尾典子君) 失礼いたします。ついでにするわということは,私は先ほど申し上げたつもりはございません。市長との座談会を催しておりますので,お申込みいただければ,例えば財政についてお話をしたいんだと言えば財政の担当の課や部長を連れてお話に参りますので,ついでにするわっていうことは申し上げたつもりはございません。
○5番(守屋基範君) 先ほどの表現は失礼いたしました。 今,市長の座談会のような形で,実際に財政に関してもそういう団体が市長とのやり取りの中で,懇談会等でいろいろ真摯に議論するということで理解をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
それから,3番の福祉事業で削減を検討してる事業,かなりやり取りをされて,先送りみたいといいますか,今検討中みたいなのもあるんですけれども,実際にやり方なんですけども,協議せずに出してというよりは,1年,担当者が結構委託事業なんかの場合は中の内容までかなり把握してないということもあったりするんで,実際に1年そういう期間を設けてやったほうがよかったんではないかなというふうな,そういうことを思っております。
はい。それから,4項目めなんですけども,今,特別交付税の関係ですけれども,国から交付税で賄える事業をいろいろと計画をされています。財政健全化がなければ,そこまで考えることもなかったのが現状ではないかと思います。企画政策課が笠岡市の政策づくりの部分でイニシアチブを取っていただきながら,積極的に補助事業や交付税措置による財源確保の取組,機運を全庁的に進めてほしいと思います。これについて,政策部長のほうで何かお考えがあればお示しください。
○政策部長(大須賀寿樹君) 財政健全化プランの取りまとめが行われまして,その場のこの中には今後の将来の笠岡市のビジョンということも盛り込ませていただきました。それを実際に,現実に実行していくために,庁内で横断的に機動的に協議ができるタスクフォースを立ち上げましたので,立ち上げ以降,毎週のように庁内の重要事項について様々なテーマで議論を重ねております。今後,さらに力を入れていく分野として,いわゆる財源の確保とか,そういうものもあろうかと思いますので,そういったものをどんどん取り入れて,庁内の議論を活発化させていきたいというふうに考えております。
○5番(守屋基範君) ありがとうございました。引き続き,よろしくお願いいたします。
今回,副市長を中心に大胆な財政健全化プランが構築されましたが,副市長は岡山県の県職員出身であり,県庁とのパイプが太いと思われますが,今回の財政健全化について県へのアプローチをされていれば,そのことをお聞かせください。
○副市長(那須信行君) 再質問にお答えします。 まず,1つ申し上げておきますけれども,私が中心となって財政健全化プランを作成したということではございません。全庁を挙げて取り組んだということでございます。その辺は誤解のないように申し上げておきたいと思います。
健全化プランに関連して,県のほうにどういったアプローチをしたかということがポイントだと思いますけれども,策定過程,財政状況収支見通しを作成した段階,それからプランの素案,そういったものを制作した段階で県のほうに状況を説明をして,様々な観点から県のほうにアドバイスをいただくというような取組は行ってきました。その中で,特別交付税なんかにつきましても,県の知見の中で活用できるものを御紹介いただいたりとか,そういったことは実際の実績としてございます。
全般として,県のほうからこのプランに関して直接的な補助金等があるわけではございませんので,いろんな観点で今後プランを推進していく中でアドバイスを受けていきたいと思ってます。 〔
パブリックコメントの中にもあったんですけども,笠岡市にとって,県との連携は大きいと思います。市民の方からのメッセージの中に,井笠の振興局,地域振興室がなくなってから県とのやり取りが激減をして,つながりがなくなった,これも県の財政再建のあおりではないかと思ってるんですけども,副市長の県への大胆なアプローチでこのピンチに県との新たなる関係構築を進めていただきますよう,よろしくお願いします。今,考えられる,これからの県と市の連携,それについて何かありましたらよろしくお願いします。
〇副市長(那須信行君) 再質問にお答えいたします。
県としっかり連携をしてほしいという御趣旨のことだと思っておりますけれども,確かに井笠県民局から今,支局という形になって,機能は少しほそぼったということはございますけれども,それで県と市の関係が離れていくということは寂しい話でございますので,私もこちらのほうに県を退職後来させていただいておりますので,できるだけ県のほうに通い,それから私だけでなくて,職員もしっかり県の職員と日頃からつながるという意識を持って取り組んでいくということが,これから県と市の関係をつくっていく重要な要素ではないかなと思ってます。
県からだけではなく,市のほうからもしっかりアプローチをして情報交換を図っていくのが大切だと思っております。その中で,私もしっかりできることを考えていきたいと思います。
○5番(守屋基範君) ぜひともよろしくお願いします。
調べたら,高知県なんですけども,高知県って2003年から県の職員が地域支援企画員みたいな形で市町村に入ってるんです。実際に,今7ブロックに64名の地域支援企画員を配置してると,そのブロック自体が集落活動センターみたいな形で,いわゆる小規模多機能みたいな,そういう機能を持ったところに部長級と課長補佐級と,それぞれに入ってるような,そんな感じで,やっぱり地域自体はこれからが本当に大変な中で,県もある意味こういう地域に一緒に入っていただきながら共にやるというような,そういうスタンスも必要ではないかなと,これは意見ですけれども,お願いします。
○5番(守屋基範君) 福祉と子育てについては削減していないと,さきの12月議会で私に対しての市長の答弁でおっしゃったんですけども,パブリックコメントの中にこれだけ多くの意見が出ている,この現状を市長,どう捉えられますか。
○市長(栗尾典子君) 福祉と教育は削減していないとは私は申し上げておりません。細心の注意を払って削減の案に盛り込んだというふうに表現したと思います。
いろいろな御批判はありますけれども,今まで手をつけられなかった部分に関しても,1つずつの事業を精査していく中で検討した結果でございますので,御批判等いろいろあっても,それは真摯に受け止めたいというふうに思っております。
○5番(守屋基範君) この項の最後にお尋ねをします。
福祉を守る心は市長の中にあるかどうか,お尋ねいたします。
○市長(栗尾典子君) あります。
○5番(守屋基範君) 安心しました。ありがとうございます。
○5番(守屋基範君) それでは,2項目めは新年度予算についてです。
2項目めの1,笠岡市財政健全化プランにより10億円程度の削減と5億円の行革債の借入れをするという中で,新年度一般会計予算は過去最大の275億円になると報道されています。市民の方々に対しては,これまでの財政健全化に矛盾する内容となっている,その内容をお尋ねいたします。
令和7年度の一般会計当初予算は,財政健全化プランの内容を反映させた予算案でございますが,予算規模が最大となった主な要因は西部衛生施設組合の新ごみ焼却場建設費負担金及び市民病院建設に係る補助金によるものでございます。これらの要因を除くと,一般会計の予算額は前年度予算と比較してマイナス2.7%,約7億円少ない予算規模となっております。
2番目,財政健全化の中で,栗尾市長の初めての新年度予算となる。市長が目指す笠岡像,そして何よりも優先した新年度の施策についてお尋ねいたします。
まず,私が目指す笠岡像についてですが,讃志会の代表質問でもお答えいたしましたとおり,第8次総合計画審議会で対話と調和と連携で夢と笑顔が広がるまちづくりをお示ししました。引き続き,審議会で委員の皆様に御審議いただき,策定作業を進める中で新たな都市像の検討を深めてまいりたいと考えています。
また,優先した新年度の施策については,令和7年度当初予算の提案説明で御説明したとおり,財政健全化プランでお示しした目指すべきビジョンの,暮らしを支える,まちを整える,子供を守る3つの柱に沿った施策を重点的に実施することとしており,公約としても掲げている第2子以降の保育料無償化,令和8年度からの高校生までの医療費無償化に向けた準備費用を予算化いたしました。また,臭気対策については市民モニターや臭気報告アプリのAI実装,臭気分解ネットの設置など,多面的に取り組むこととしております。
3番目,国の物価高騰対策に準じて,本市でも対応策を各分野にわたり検討され,具体的に施策として提案されています。
ア,笠岡諸島の離島航路燃料価格高騰対策支援事業として,補助航路以外の航路事業者への支援が予定されています。これに関連いたしまして,航路再編への事業者との話合いを市長自らも出向いて進めるとのことでありましたが,その進捗状況をお尋ねいたします。
将来の航路維持に向けた事業者との話合いについてですが,まずは航路運航の現状について情報共有を図ることを目的として,昨年6月に航路事業者3社に市役所にお越しいただき,意見交換会を開催させていただいたところでございます。意見交換会後も私が直接足を運ぶなどして,各航路事業者の皆様と意見交換を行っております。今後も,引き続き意見交換,情報共有を行い,日程が整えば2回目の意見交換会を開催してまいりたいと考えております。
イ,笠岡市内の指定管理事業者において,物価高騰や人件費アップに伴う指定管理料金の赤字補填等について考えをお尋ねします。
指定管理委託料については,物価高騰や人件費の上昇を考慮して積算し,予算計上を行っております。しかし,予算を超える物価上昇となった場合には,個別に対応を検討してまいります。
ウ,蛍光灯の2027年問題として,製造,輸出入が2027年までに段階的に禁止されます。それに伴い,省電力化の観点からもLEDの設置が事業所,家庭,街路灯に至るまで幅広い対応が求められています。これらに関した物価高騰対策の事業についてお尋ねいたします。
照明等の機器をLED化し,省エネ化することで,二酸化炭素の排出削減を図るとともに,高騰している毎月の電気料金等の負担軽減も図れることから,事業所向けと家庭向けに物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金による補助を新たに行いたいと思っております。
まず,事業所向けといたしまして,中小企業者等省エネ機器更新支援補助金を計上しております。市内の中小企業者や小規模企業者が,工場や店舗,事務所等で使用する設備や機器を更新し,省エネ化するためのLED照明や空調機器等の購入費と,それらに係る運搬費及び設置工事に要する経費の一部を補助するものでございます。
次に,家庭向けといたしまして,省エネ家電等買換え促進補助金を予定しております。その対象品目として,LED照明に加え,エアコンや冷蔵庫等の省エネ家電への買換え費用の一部を補助するものでございます。
さらに,同じ交付金を活用し,街灯設置事業補助金として,団体及び個人が主体となって設置する公共性のある街灯の工事費について,新規の設置に40%,修繕に50%の補助金を還元し,LED化の推進を図っているところでございます。
今後も,事業所や市民の方々への周知をしてまいりたいと考えております。
4項目め,観光施策について。令和7年新年度の観光事業の目玉についてお尋ねいたします。
令和7年度の観光事業といたしましては,本市が保有する豊富な地域資源のポテンシャルを生かし,今後戦略的に事業展開していく上で必要となる観光資源の調査事業に取り組みたいと思っております。
具体的には,笠岡湾干拓地や笠岡諸島などの市南部だけではなく北部にも目を向け,観光資源がどのように活用できるかということについて,国の財源を活用して様々な可能性を調査してまいります。市内だけでなく,井笠圏域,備後圏域等の広域連携を視野に入れた事業展開についても検討し,関係人口,交流人口の増加を目指してまいります。
以上でございます。
5番目,地域コミュニティー等について。
ア,令和7年度に,まちづくり協議会や公共施設の使用料見直しを計画する方向性を持っているとの話があったと思いますが,今後の予定についてお尋ねいたします。
今後のまちづくり協議会の見直しにつきましては,地域の各組織において担い手不足や活動の重複などの課題があることは行政として認識しております。また,議会からの政策提言の中でも,地域組織の目的を明確化し,整理することで重複をなくすことを提言されています。また,このたびの財政健全化プランのパブリックコメントでは,各種団体で構成員や活動内容の重複を解消するため組織の統合が必要であるなど,市民の皆様からの御意見もいただきました。今後,各組織の持続可能なまちづくりのためにも地域組織の統合再編を進めてまいります。
公共施設の使用料につきましては,令和7年度中に見直しを行うこととしており,令和8年度予算に反映できるように進めてまいります。
イ,今井地区を想定して進められているまちづくり協議会と公民館との拠点づくりの方向性についてお尋ねいたします。
今井地区につきましては,今井地区まちづくり計画に基づいて旧今井小学校を活用し,まちづくり協議会と公民館が同一施設に入ることにより,公共施設の集約化だけでなく地域住民の多様な活動の場としての機能を強化することが可能となります。
財政健全化プランの中の公共施設の在り方見直しにもあるとおり,公共施設につきましては,人口構成や社会ニーズの変化,地域の実情を鑑みて,必要なサービスの維持や目的の転換を図りながら統廃合を積極的に進め,将来に大きな負担を残さないようにしていきます。
地域の拠点についても,持続可能なまちづくりが行えるよう,地域の皆さんの声をお聞きしながら,統合や見直しによる再編に取り組んでまいりたいと考えております。
ウ,敬老会,市美展の今後についてお尋ねいたします。
ここ数年,敬老会への出席者が減少する地区が増える傾向にあります。さらに,温暖化による猛暑のため,高齢者が敬老会に出席するには厳しい状況が続いており,この時期に開催することが実情に合ってないと考えております。加えて,長年,地域で敬老会を担ってくださっている方々の高齢化が進んでおり,負担感も増しています。これらのことから,敬老会そのものの在り方を見直しすることにいたしました。今後,御長寿をお祝いする祝賀行事は,地区の実情や実施団体の状況に合わせた形でお考えいただきたいと思います。市としては御長寿をお祝いする気持ちをお伝えしたく,80歳,88歳,90歳,99歳の節目年齢の方々にお祝いのメッセージカードをお送りしたいと考えております。 次に,2
笠岡市美術展はこれまで47回にわたり開催し,市民の皆様の創作意欲を育み,地域の文化芸術の発展に大きく寄与してまいりました。しかしながら,近年は出品点数の減少が続いており,出品規格の変更や新規出品者の発掘など,様々な工夫を重ねてまいりましたが出品点数の改善には至りませんでした。文化振興事業を持続可能な形で継続していくためにも,財政状況を一つのきっかけとして市美術展の在り方についていま一度見直すこととし,今年度をもって終了するという判断をいたしました。
しかしながら,笠岡市として文化芸術を大切にしたいという思いはこれまでと変わりはありません。今後につきましては,新たな形で作品を発表できる機会を創出し,より多くの方に文化芸術を楽しんでいただける場を模索してまいりたいと考えております。今まで出品してくださった皆様の思いを大切にしつつ,市民の皆様がより身近に文化芸術に触れ,創作や発表を楽しめる環境を整えてまいります。
2項目めです。
ピンチはチャンスとも言われます。パブリックコメントの中にもありましたが,実は笠岡市政で予算を前年度に皆さんで集まって議論するというのは多分初めてだと思うんですよね。それに関しては,パブリックコメントでもかなり評価されてる方もいらっしゃいました。
実際に,その中で市民は何ぼか我慢する部分は仕方ないと思うんですけど,実際に何年かすると何かバラ色の夢がとか,そういうところを若干求めたりするんで,そういうことも含めて今後とも市民が夢を見れるような,そういうビジョンも含めてリーダーシップを取っていただければなと思っております。
あと,3項目めの物価高騰対策,これに関しては,島の船舶の航路に関してはかなりこれから本当に大変な時期に入ってくると思います。先般も船に乗っていると,燃料の高騰,これに関してはもう手を挙げるみたいなことを言っている業者もいらっしゃいましたけれども,実際に行政として話をするときに,何かこうきっかけということも含めて,今回こういう国の事業,これを一つのきっかけとして航路事業者に説明をすることも含めて,そういう手法というか,実際にこの補助金なんですけど,いつ頃,どんな感じで申請とか募集開始とかになるのかお尋ねいたします。
○政策部長(大須賀寿樹君) この離島航路燃料価格高騰対策につきましては,令和5年度にも1度やらせていただいております。今回,大きな仕組み自体は変更しておりませんので,もし予算が成立すれば,4月1日から用意ドンで動けるかと思っております。
今,航路事業者の皆さんの厳しい現状とか,そういうものは伺っておりますんで,4月1日になれば,担当者がすぐに申請書を持って直接説明に上がって,すぐに動けるようにしていきたいというふうに考えております。○5番(守屋基範君) よろしくお願いいたします。
イの項目,指定管理についてです。
指定管理は5年契約で受けてる事業者にとっても,この物価高騰対策,このあおりはかなり大きいものだと思います。その赤字補填とか,その他一定のガイドライン的なそういうものは設けられているかどうかお尋ねいたします。
○総務部長(田尚史君) 指定管理等の委託料について,物価高騰が心配されるということでございます。先ほどの答弁でもございましたように,一定の物価高騰については現段階の状況に応じて予算については配慮したようなことで計上させていただいております。今後につきましても,ガイドライン的なものは個別の委託先の事情でありますとか財務状況についてはそれぞれ見させていただいて,必要に応じてそうした物価高騰に対する委託料等の上乗せについては検討してまいりたいというふうに考えております。
○5番(守屋基範君) 物価高騰と併せて,実際に賃金アップとか人件費の問題も多分これから出てくると思うんです。
あともう一つは,ただ単に管理をするのと,実際に有資格者をそこに入れて管理をしてもらうとかというふうになると,賃金の面とか,そこの施設にちゃんとした正社員,給料も何ぼか保証されたような,そういう経費,そういうあたりもいろいろ考えていただければなというような感じで思ってます。住民ニーズのある施設については,そういう経費だけではなくて,内容も十分見ていただいて,それぞれに合った配慮をしていただければなと思っております。
例えば,初年度から何年たって,もうこれぐらい上がったんだからみたいな話の経費面ではなくて,実際にその施設をいかにそういう指定事業者が活性化をしながら,目的をどこまで達成しているかというのも事業者と,あと市とで共有をしながら,そこも評価基準にしていただきながら特色がある指定管理のものとして考えていただければと思ってます。どうでしょうか。
○総務部長(田尚史君) 個別の対応になろうかと思いますので,有資格者でありますとか賃金のアップにつきましても,必要に応じてその都度検討させていただきたいと思います。
5番(守屋基範君) よろしくお願いいたします。
4番目の観光施策についてです。
部長のほうから,プランづくりという話がありましたけれども,失礼な話,いまだにプランづくりかなみたいなこともあるんですけども,実際に笠岡の観光の特徴は,部長も言われましたけれども笠岡諸島だと思っています。自然環境とか伝統行事のほかに,一番の資源は島の人々,島の方だと思うんです。今年度も北木島で人材育成事業を展開してきましたけれども,私の考えとしては,島は陸地部の20年先取りだと思います。実際に,過疎,高齢化,地域課題の先進地ということで,実は陸地部の高齢化は島の20先の高齢化率と大体一緒だということを思ってまして,島は陸地部の20年先取りみたいなことで,本当に日本の縮図だと思ってます。
先日,島の水洗がされてないという話も出ていましたけれども,現在より一層の担い手の減少で,景観保持,水洗の整備も本当に大変な状況になっています。今,地域の人に,どれだけ観光について考えてほしいかなっていうときに,これまでは,例えば100人,人がいて,実際に人が50人減ったとします。自分の足を確保しようと思うと,その50人分を観光客で入れるということで100人を確保すると,そういうことが必要になってきます。実際に,観光客を入れることが自分の足を確保するという,そんなことも含めて,地域の人が自分事として観光を考えていただくという,そんなことも含めて,実際に島の中でツアーもされたりしてるんですけども,本当に受入れが大変な状況というのが今すごくあります。
観光振興という視点だけではなくて,地域のコミュニティーを守るというふうなことも含めて,ただ観光で人を入れるんじゃなくて,地域をどう観光でサポートするか,そういう考え方もこれからの笠岡諸島の観光には必要ではないか。例えば,草刈り体験とかも含めて,観光から体験,それを交流人口につないで,移住とかにもつながるという,そんな感じの取組が求められていると私は思ってます。
栗尾市長に御質問するんですけども,実際に笠岡諸島の,例えば島のコミュニティーとか観光振興等についてはどういうふうなお考えをお持ちか,お聞かせください。
ただいまの御質問の中で,島についてというふうにおっしゃられたかと思いますけれども,笠岡市においては,島だけではなくて様々な観光のポテンシャルを持つところが多くあると思います。先ほどの市長答弁でも申し上げましたけれども,本年度はそういった笠岡市,北から南,島まで含めて,どういった戦略でこの観光に取り組むのかというようなことを事業として考えるという事業を上げております。そういったことで,島のみならず,全市内のポテンシャルを総合的に戦略的に観光資源としてどう生かすかというふうに考えてまいりたいと思っております。
○5番(守屋基範君) 笠岡市全体を考えてプランづくりをするという,そういう答弁だったと思うんですけども,実際に大体補助をつけてプランづくりをする,ほとんどコンサルが来てやって,お金はコンサルが持って帰るみたいな形で,実際にそれが,例えば地域の人の声がどれだけ反映してるとか,そういうところも含めて,この計画のやり方,例えばメンバーも含めて,実際にやるそれぞれの地域の人,どれだけメンバーにして吸い上げるかとか,そういう計画づくりの基本についてはどうお考えでしょうか。これは部長でいいです。
○産業部長(前川英之君) 守屋議員の再質問にお答えをいたします。
これまで観光のいろんな計画をつくる中で,行政主導でやってきたというところを多少なりとも自覚をしております。今後,実際に計画をつくって,それを実行していくということになりますと,地域の方をどうやって巻き込んでいくか,その地域の方に実際にやっていただくことも出てこようかと思いますので,実効性を高める上ではそういった地域の方との関わりっていうのは大切だと思っておりますので,そのあたりを注意しながら企画のほうは検討してまいりたいと思います。
○5番(守屋基範君) それでは,次のイ,議会のほうからまちづくりでも政策提言が出てますけれども,実際に今,市のほうでの進捗状況,対応についてお聞きいたします。
○政策部長(大須賀寿樹君) まちづくり協議会の在り方っていうことの進捗状況についての御質問かと思いますけども,先ほど申し上げました,庁内のタスクフォース会議のほうでテーマとして関係部署に集まってもらって議論を始めたところでございます。
単純に,まちづくり協議会だけじゃなくて,様々な組織が関係してきますし,あともう一つは拠点となる施設,そういった部分でも大きく関係してきますんで,庁内でもいろんな部分が連動していくかと思ってます。
今後,この議論が活発化していくかと思うんですけども,横の連携をしっかり取りながら検討を進めていきたいというふうに考えております。
○5番(守屋基範君) 今後とも,市長のよく言われる小規模多機能自治,これを目指してということなんでしょうけども,実際に市長のイメージする小規模多機能自治というものについて御説明お願いします。
○市長(栗尾典子君) 小規模多機能自治についての再質問にお答えします。
小規模多機能自治,いわゆる先進地域として雲南市が挙げられると思いますけれども,雲南市の事例で見ますと,地域コミュニティセンターということで,コミュニティセンター化をされて,さらにそれを一歩進めてコミュニティセンターがNPOになるというようなところまで進化しているというふうに仄聞しております。
そういったことで,笠岡市内においても各地域で拠点をそれぞれ決めて,その拠点の中にコミュニティセンターが作れるような,そういったイメージを持っております。
○5番(守屋基範君) ありがとうございました。
私も雲南とかは何回か行ったことがあるんですけども,実際に笠岡においても今の今井の現状自体がそういう小さな拠点的な部分で,そういう体をなしている。それについてまちづくり計画とか施設の利用計画とかをつくりながら補助を受けている,それこそがある意味,小規模多機能の推進モデルではないかなと思ったりするんですけども,そういうところを,例えば生かして,もっとこう分かりやすく,ほかのまち協のモデルとして,何かある意味,一緒にするだけが目的で何かその精神が入ってないみたいな,まだまだ検討段階だとは思うんですけども,はい,そこら辺のことをお願いいたします。
○政策部長(大須賀寿樹君) 市長が申し上げた小規模多機能自治ということと拠点の集約っていうのは,全く同じかっていうと同じものではない。ただ,強く関係しているというものだと思います。今井地区については,ある種,旧今井小学校のほうに拠点が集約化されてきたという形になっております。これを機会にして,さらにその地域をどういうふうに運営してくのかということについて議論するきっかけになっていただけるといいんじゃないかというふうに考えております。
○5番(守屋基範君) ありがとうございます。
今回,機構改革で協働のまちづくり課がまちづくり課に変更されますけれども,実際にこのコミュニティーに関して言うと,協働って何かなみたいな話のときに,2つ対象。市が協働する相手としては,1つが地域組織,地縁組織としてのまちづくり協議会,もう一つが支援組織としての目的を持った活動団体,NPO等,そういうところと連携をして,市制の中で同じ公共を進める対等なるパートナーとして,そういうNPOとか,そういう支援組織に対する市長のお考えをお聞きしたいなと思ってます。
○政策部長(大須賀寿樹君) 志縁団体についての御質問かと思います。
笠岡市では,先ほど議員がおっしゃったとおり,地縁団体としてのまちづくり協議会と,あと志縁団体,まさに同じ目的,趣旨に賛同する人たちが集まって,まちづくりですとかそれぞれの目的を達成するために活動されている方々,市民活動団体という言い方がいいのかもしれませんが,そういった団体について支援をしているところでございます。
いずれも,市民活動支援センターのほうで支援をしてしながら,または交付金という形でもまちづくり交付金の中には支援型のまちづくり交付金というものがございますし,そういったもので支援をしているところでございます。
○市長(栗尾典子君) 私の考えを申し上げます。
支援団体という言葉で,少し,どの範囲までを示されているのかということでお答えが違っていたら申し訳ないんですけれども,まちづくり協議会,そしてNPOだけではなくて,地域には様々な,もちろん公民館であったり,そして愛育委員,栄養委員,PTA,消防団,本当に様々な団体がまちづくりに関わってくださっております。その全ての方々が支援の団体であり,協働の相手だというふうに認識をしております。
○5番(守屋基範君) 実際に,そんな感じで全てなんですけども,例えば行政とのやり取りをするときに,公共を担う,その分野でかなり組織化されて,公共のパートナーになれるところが,これから先,行政も財政の問題とかもあって,直接やるよりはそうやってNPOとか,そういう地域ボランティアとかがやるほうが効率的にいく場合も結構あると思うんです。そういうところも含めて,今回財政健全化で活動費が削減され,結構何か違和感を覚えている方が多いと思うんです。実際,そこも含めて,これからは市長の代弁者として,その団体に対応する職員がいかにそういうところのケアができるかとか,今の福祉もそうなんですけど,寄り添い方,そうことでずっとそこら辺の問題解消をやっていっていただければなと思ってます。
それから,続いていきます。敬老会とか,あと市美展については実際に市民の皆さんからいただいた声をそのまま出しております。でも,実際にやめるときにはある程度次のことを考えてやめてほしいなというのが一つと,実際にこの時期にやめたら,笠岡市は財政が苦しいから敬老会をやめたんかみたいなとか,文化を捨てたんかみたいなことになってくると思うんで,ある意味,そこら辺の見せ方とかというか,そこら辺は何か工夫が要ったんではないかなと思いますが,森山部長。
○教育部長(森山一成君) 教育部ですので,美術展について述べさせていただこうと思います。
財政健全化プランが出て,どういうふうに文化振興事業を続けていくのかということをいろいろと庁内の中,それから文化振興事業委託料,委託している先,文化連盟の皆様とも話を続けていきました。限られた予算の中で,どうやって市民の文化活動を支援したり,それから持続可能な文化事業をこれから後も守っていかないといけないという中で,どういった工夫ができるのか,時にはやめることも必要ですし,発展させることも必要だという中で一緒になって考えることとしてきました。文化連盟さんはこのまま継続したいという強い思いを持っておられましたが,これをきっかけとして文化事業全体を見直していく中で,笠岡市の新しい文化の発展というものを考えていきましょうということで最終的には御理解をいただいたということです。
市美展に関しましても,6つのジャンルでずっとやってきましたけども,市民の中からは,現代アートであったり,デジタルアートであったり,デザインの分野であったり,いろんなことの提案もあったりしたんですけども,審査員の確保ができないということで,そのあたりは実現できていなかった,そういったことも含めて,今まで課題とあったものも見詰め直して,今度は新たな文化祭が今ありますので,その中で発展的な形で文化事業を進めていきたいということを考えてきました。
内部の中でとか関係する団体の皆様とは協議を重ねてきて,突然ということではなかったんですけども,どうしても美術展が年度の終わり頃,2月頃にあったということで,早くからの発表は意欲をそぐのではないかという考えもありましたから,最終的には表彰式の閉会の場で私のほうから今年度をもって終わりということ,それと皆様方にはいろんな文化芸術の発表の場は必ずつくるので,魅力を伝えていく伝道師にもなってもらいたいということ,それから市民にも意欲をそのまま持っていただいて,継続した形で文化の事業は続けていきますということを進めておりますので,今後は,先ほど言いましたようなジャンルも含めて,若い人たちがどんどん発表する場,チャンスをつくるということを考えておりますので,しっかりと市民の皆様にも御協力いただきながら進めていきたいと思っております。
○5番(守屋基範君) ありがとうございました。
今回,財政再建,健全化ということで,市民の方が市制にちゃんと真摯に考えていただいて,これからが本当にスタートだというふうに思っております,議会議員としても,市民の声をこんな感じで議会で市民の声を代弁をさせていただくことによって,市民の人が私をある意味アバターと考えて,それでやり取り,そういうことで真摯な議論ができることをこれからもやっていきたいなと,今回はどうかなというとこはありますけれども,今回を最後に部長職を解かれる方も何人かいらっしゃいまして,本当に御苦労さまでした。今後とも笠岡の未来のために一緒に頑張らせていただければと思います。今回は結構失礼なことも言いましたけれども,本当に笠岡のことを思って,笠岡をどうにかしたいという気持ちでいっぱいです。お互いに頑張っていこうと思いますので,よろしくお願いします。
以上です。終わります。
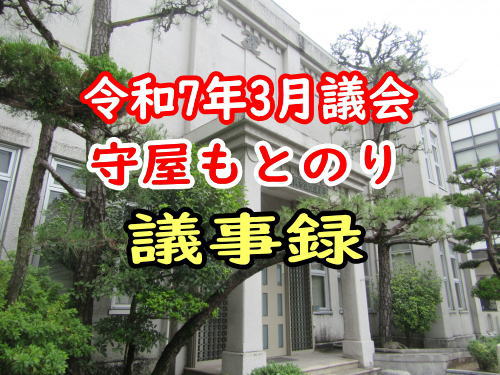
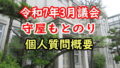
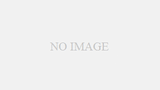
コメント